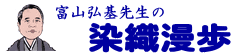「草木染」、これほど的を射た言葉はめずらしい。自然界の植物を染料として使途や布を染めることを指す用語として、今日では知らない人はいない。ところがこの用語は、昭和4年に島崎藤村と親交のあった長野県出身の文学者・山崎斌氏(やまざきあきら/1892~1972年)が命名した創作語であるとの認識は、染織界でも極めて薄い。
“草木染”は染織専門用語というより、一般の人たちに合成染料と対極にある伝統的な天然染料の存在を知らしめる言葉として、文学的な感性で造られたもので、この言葉の誕生によって、戦前においても伝統染織の見直しを促すことになったし、戦後には“草木染ブーム”を巻き起こすことにつらなった。
明治3年にドイツから合成染料が京都に初めて輸入され友禅染め、西陣織の染色に大きな影響を与えた。同10年代には全国各地の染織産地へも燎原の火の如く広がり、瞬く間に天然染料を凌駕する。さらにインジゴピュアー(合成藍)が同30年にドイツの馬獅子(バジェッシェ)染料会社で開発されると勢いは加速、大正・昭和へと続く。辛うじて阿波藍、紅染め、紫根染め、大島紬、黄八丈、琉球染織など伝統的な特定の染織品は合成染料の侵食を防ぐことができた。
昭和3年、柳宗悦氏の民芸運動が興ると、古き佳き物への再評価が高まり、文学界からも伝統工芸の復興に立ち上がる人たちがあった。山崎斌氏は郷里の養蚕不況の対策として副蚕糸による田舎手織物を提案、自ら植物染料による手織りに関わり制作。合成染料使いの織物と区別するために昭和4年に「草木染」と命名して信濃手工芸伝習所を松本市に設け、翌5年には東京銀座資生堂で「第1回草木染手織復興展覧会」を開催した。当時の新聞、ラジオ放送で報道され、植物染料を使う織物が再び脚光を浴びることになった。
昭和7年に草木染は商標権を得たが、子息、山崎青樹氏に引き継がれてからも、他の染織家が無断で名称を使っても余程のことがない限り抗議されることはなかった。その理由は「草木染を志す人は善なる心をもっている」と信じ、それ故に植物染料でよりよい染織の制作をめざすのなら寛容するとの温かさがあった。
「草木染」の三文字は合成染料による市場の席巻に敢然と立ち向かうエネルギーを、多くの染織家に与えた。そして岩波書店刊『広辞苑』(平成3年/1991年)改訂版から「草木染」が項目に収録されるにおよんで、後継者の青樹氏は今や草木染は公知公用語になったと判断、商標権を放棄することを英断された。
日本では明治以降において天然染料を使うことを指して学識研究者、作家はそれぞれに好みの言葉を造語しているが、社会日常語となった草木染のほかに戦前では、植物染研究の先駆者・本草学者の白井光太郎氏は「染料植物」、染織書誌学者・後藤捷一氏は「和染(わぞめ)」、上代染織史学者・上村六郎氏は「本染(ほんぞめ)」。昭和31年に記録作成を講ずべき無形文化財指定の後藤博山(ごとうはくざん)氏は「古代植物染」。戦後派の松本宗久氏は「草根花木皮染」。前田雨城氏、吉岡常雄氏、木村光雄氏その他の学識者は「天然染料」の名称を主に、好まれているが、一般の染織家の大半は草木染(め)を選択している。また「花染」も登場した。
“草木染”は染織専門用語というより、一般の人たちに合成染料と対極にある伝統的な天然染料の存在を知らしめる言葉として、文学的な感性で造られたもので、この言葉の誕生によって、戦前においても伝統染織の見直しを促すことになったし、戦後には“草木染ブーム”を巻き起こすことにつらなった。
明治3年にドイツから合成染料が京都に初めて輸入され友禅染め、西陣織の染色に大きな影響を与えた。同10年代には全国各地の染織産地へも燎原の火の如く広がり、瞬く間に天然染料を凌駕する。さらにインジゴピュアー(合成藍)が同30年にドイツの馬獅子(バジェッシェ)染料会社で開発されると勢いは加速、大正・昭和へと続く。辛うじて阿波藍、紅染め、紫根染め、大島紬、黄八丈、琉球染織など伝統的な特定の染織品は合成染料の侵食を防ぐことができた。
昭和3年、柳宗悦氏の民芸運動が興ると、古き佳き物への再評価が高まり、文学界からも伝統工芸の復興に立ち上がる人たちがあった。山崎斌氏は郷里の養蚕不況の対策として副蚕糸による田舎手織物を提案、自ら植物染料による手織りに関わり制作。合成染料使いの織物と区別するために昭和4年に「草木染」と命名して信濃手工芸伝習所を松本市に設け、翌5年には東京銀座資生堂で「第1回草木染手織復興展覧会」を開催した。当時の新聞、ラジオ放送で報道され、植物染料を使う織物が再び脚光を浴びることになった。
昭和7年に草木染は商標権を得たが、子息、山崎青樹氏に引き継がれてからも、他の染織家が無断で名称を使っても余程のことがない限り抗議されることはなかった。その理由は「草木染を志す人は善なる心をもっている」と信じ、それ故に植物染料でよりよい染織の制作をめざすのなら寛容するとの温かさがあった。
「草木染」の三文字は合成染料による市場の席巻に敢然と立ち向かうエネルギーを、多くの染織家に与えた。そして岩波書店刊『広辞苑』(平成3年/1991年)改訂版から「草木染」が項目に収録されるにおよんで、後継者の青樹氏は今や草木染は公知公用語になったと判断、商標権を放棄することを英断された。
日本では明治以降において天然染料を使うことを指して学識研究者、作家はそれぞれに好みの言葉を造語しているが、社会日常語となった草木染のほかに戦前では、植物染研究の先駆者・本草学者の白井光太郎氏は「染料植物」、染織書誌学者・後藤捷一氏は「和染(わぞめ)」、上代染織史学者・上村六郎氏は「本染(ほんぞめ)」。昭和31年に記録作成を講ずべき無形文化財指定の後藤博山(ごとうはくざん)氏は「古代植物染」。戦後派の松本宗久氏は「草根花木皮染」。前田雨城氏、吉岡常雄氏、木村光雄氏その他の学識者は「天然染料」の名称を主に、好まれているが、一般の染織家の大半は草木染(め)を選択している。また「花染」も登場した。