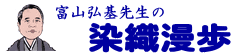古語と現代語で解釈の異なる珍現象
日本の染織史を繙くと、これは誤りではと疑問を抱く事柄が結構多い。しかし、それが学術研究者の認知したものであると常識として罷りと居る。その認知そのものが、あいまいに決められたものでも、余程の根拠を示さない限り、それを覆すのはむつかしい。
その一つが「辻が花染(つじがはなぞめ)」である。この常識こそが誤りであるということは、京都の古美術界では言い古されて来たが、商売がら表立って言えなかったという経緯がある。だが近年になって、それを裏付ける待望の学説が河上繁樹氏(関西学院大学教授)によって提起され、溜飲を下げた人は多いはずである。私もその一人である。
「辻が花染」という音韻の響きと文字の美しさには、いかにも華やいだ、そして雅な染め衣を思い起こさせる。博物館で出陳される辻が花染小袖を鑑賞すると、この彩りと模様を演出してくれる当時の人々を堪能させた染師の磨き抜かれた感性に、称える言葉が思いつかないほどである。
薄地の練貫(ねりぬき/タテ生糸・ヨコ練糸の白生地)や半練の絹の白生地を基布に、麻の諸撚糸(もろよりいと)で模様の縁を縫い始め、帽子絞(ぼうししぼり)など幾種類かの絞り技法で染め分け、これに摺箔(すりはく/型紙で糊置きして箔押し[金箔・銀箔を貼り付ける])、縫(ぬい/刺繍)、黒の描絵(かきえ)と線描、色挿しで加飾する小袖の模様染めを今日では固有名詞的に“ツジガハナゾメ”と呼んでいる。それが誤りであることがほぼ立証されたこと。
平安・鎌倉時代は唐織など紋織の先染物(先に糸を染めて織る物)が、支配階層の正装衣服で、白生地に模様を施す後染物(白生地に模様染めする物)は格下に見られていた衣装感が、室町時代には小袖が正装に取り入れられる時流に乗って、模様染め技法と衣装が際立って発達する。
辻が花染の萌芽は室町期の半ば、これが桃山時代に大輪を咲かせ、気宇壮大な太閤秀吉好みに合ったのではないかと思わせる。ところが江戸初頭には忽然として表舞台から姿を消すという、不可思議なことが起きる。
もしかして、その背景に歴史的な悲劇が隠されているのではないかと思わせる出来事がある。
文禄4年(西暦1595年)旧暦7月に関白豊臣秀次が養父の太閤秀吉の命により高野山で自刃、翌8月2日には秀次の子女と妻妾ほか一族39名が、京洛鴨川の三条河原の処刑場で露と消えるという、秀次事件。その人たちが召していた艶やかな衣装類(辻が花小袖?)が京雀の噂にのぼり、染匠たちも気が失せ、やがて辻が花染は廃れるというストーリーが伝聞にある。
その旧処刑場にほど近い三条木屋町下ルに、秀次一族の菩提所となった瑞泉寺(ずいせんじ)が現在も残っている。慶長16年(西暦1611年)に角倉了以が高瀬川開削中に埋葬塚を発掘し、供養のお堂を建立、のちの瑞泉寺となるが、同寺には秀次一族ゆかりの辻が花小袖やその他の小袖の貴重な裂々が保存されており、これらは「瑞泉寺裂」と呼ばれている。
さて、ここで明解に指摘しておきたいことは、この時代の「辻が花染」とは、主に麻地の絞り染め、模様染めした夏の帷子の名称であったこと。つまり現代の人たちが素晴らしい小袖だと感嘆している「辻が花染小袖」は、単に縫箔絞の小袖の中に分類されるもの、特別な名称はなかったという実体が、近年の研究で明らかになってきた。
染織学識者の間でも早くから、この名称の是非に付いて議論はあったが、河上氏の学説が浮上するまではこれを検証する人はいなかった。
では何時、誰が「辻が花染」の名称を取り違えて、それが昔からの名称であるかのように固有名詞化したのかを探索すると、戦前の大正から昭和にかけて京の古美術界にこの人ありきと評された野村正治郎氏、その人であるとの見方が最も有力視されてくる。
では、どうして名称を取り違えることになってしまったかについては、次号で詳細を記したい。
その一つが「辻が花染(つじがはなぞめ)」である。この常識こそが誤りであるということは、京都の古美術界では言い古されて来たが、商売がら表立って言えなかったという経緯がある。だが近年になって、それを裏付ける待望の学説が河上繁樹氏(関西学院大学教授)によって提起され、溜飲を下げた人は多いはずである。私もその一人である。
「辻が花染」という音韻の響きと文字の美しさには、いかにも華やいだ、そして雅な染め衣を思い起こさせる。博物館で出陳される辻が花染小袖を鑑賞すると、この彩りと模様を演出してくれる当時の人々を堪能させた染師の磨き抜かれた感性に、称える言葉が思いつかないほどである。
薄地の練貫(ねりぬき/タテ生糸・ヨコ練糸の白生地)や半練の絹の白生地を基布に、麻の諸撚糸(もろよりいと)で模様の縁を縫い始め、帽子絞(ぼうししぼり)など幾種類かの絞り技法で染め分け、これに摺箔(すりはく/型紙で糊置きして箔押し[金箔・銀箔を貼り付ける])、縫(ぬい/刺繍)、黒の描絵(かきえ)と線描、色挿しで加飾する小袖の模様染めを今日では固有名詞的に“ツジガハナゾメ”と呼んでいる。それが誤りであることがほぼ立証されたこと。
平安・鎌倉時代は唐織など紋織の先染物(先に糸を染めて織る物)が、支配階層の正装衣服で、白生地に模様を施す後染物(白生地に模様染めする物)は格下に見られていた衣装感が、室町時代には小袖が正装に取り入れられる時流に乗って、模様染め技法と衣装が際立って発達する。
辻が花染の萌芽は室町期の半ば、これが桃山時代に大輪を咲かせ、気宇壮大な太閤秀吉好みに合ったのではないかと思わせる。ところが江戸初頭には忽然として表舞台から姿を消すという、不可思議なことが起きる。
もしかして、その背景に歴史的な悲劇が隠されているのではないかと思わせる出来事がある。
文禄4年(西暦1595年)旧暦7月に関白豊臣秀次が養父の太閤秀吉の命により高野山で自刃、翌8月2日には秀次の子女と妻妾ほか一族39名が、京洛鴨川の三条河原の処刑場で露と消えるという、秀次事件。その人たちが召していた艶やかな衣装類(辻が花小袖?)が京雀の噂にのぼり、染匠たちも気が失せ、やがて辻が花染は廃れるというストーリーが伝聞にある。
その旧処刑場にほど近い三条木屋町下ルに、秀次一族の菩提所となった瑞泉寺(ずいせんじ)が現在も残っている。慶長16年(西暦1611年)に角倉了以が高瀬川開削中に埋葬塚を発掘し、供養のお堂を建立、のちの瑞泉寺となるが、同寺には秀次一族ゆかりの辻が花小袖やその他の小袖の貴重な裂々が保存されており、これらは「瑞泉寺裂」と呼ばれている。
さて、ここで明解に指摘しておきたいことは、この時代の「辻が花染」とは、主に麻地の絞り染め、模様染めした夏の帷子の名称であったこと。つまり現代の人たちが素晴らしい小袖だと感嘆している「辻が花染小袖」は、単に縫箔絞の小袖の中に分類されるもの、特別な名称はなかったという実体が、近年の研究で明らかになってきた。
染織学識者の間でも早くから、この名称の是非に付いて議論はあったが、河上氏の学説が浮上するまではこれを検証する人はいなかった。
では何時、誰が「辻が花染」の名称を取り違えて、それが昔からの名称であるかのように固有名詞化したのかを探索すると、戦前の大正から昭和にかけて京の古美術界にこの人ありきと評された野村正治郎氏、その人であるとの見方が最も有力視されてくる。
では、どうして名称を取り違えることになってしまったかについては、次号で詳細を記したい。