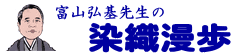江戸時代、染色は天然染材の植物・鉱物・動物の色料が使われていた。また、海外からも蘇芳・唐花・天竺花(紅花)・臙脂綿など多くの染材をオランダ・中国の交易船で輸入していた。さて幕末に黒船渡来で鎖国がとかれると、1856年(安政3)に英人W.H.パーキンが発見の人造染料の偉業を機にドイツ・フランス・イギリスなど西洋諸国も人造染料の開発を軌道に乗せた。石炭のコールタールを原料に有機化合の過程を経て製造するので、人造染料は合成染料と呼ばれるようになった。
現在は石油(ナフサ)を主原料に、繊維用(糸・布)の染色に合成染料の塩基性、酸性、酸性焙染、反応、直接、建染(バット)、ナフトール、カチオン、分散など多種類の染料が出来ている。
合成染料は古代からある天然染料と区別するために名付けたものであるが、なかには天然色素と同質のものを人工的な合成で成功したものまである。1897年(明治30)にドイツの馬獅子(バジッシェ)染料会社はインジゴピュア(合成藍)を開発、世界の天然藍製造に大打撃を与えた。日本では合成藍・人造藍・インジゴピュアの名称で知られ、阿波藍産地など蓼藍のすくも製造を衰退に追い込んだ。紺屋にとって使うに便利で、化学分析しても人造か天然か判別がつかない。そのためいま天然藍染めを求めるとすれば特定の作家物に限定されている。ほかに西洋茜が1868年にドイツで合成。アリザリン染料がそれであり、貝紫も合成染料が出ている。
さて幕末の日本は、江戸幕府崩壊を目前にした安政5年(1858)に米蘭英仏露諸国と通商条約が結ばれると、西洋科学への関心は日毎に高まる。我が国最初の化学書(舎密学)『舎密開宗(せいみかいそう)』7編21巻は天保8年(1837)に宇田川榕庵(うたがわようあん・侍医・弘化3年49歳歿)邦訳で刊行されていた。(原典は英人ウイリアム・ヘンリー著『Elements of Experimental chemistry』のオランダ語訳書)。オランダ語で化学を意味するセイミ(chemie)の表音文字に舎密を当て、化学を舎密学を呼称したのは、江戸後期から明治初期に至る期間のようである。
通商条約締結の後は、西洋文明は容赦なく押し寄せ、合成染料もパーキンが発見して6年目に京染業者が手にしたと伝聞を記述したものがある。「文久2年12月(1862)となるや紫染業の井筒屋忠助は危険を冒し私かに外人(国籍不詳)と協商し、アニリン染料を購求して是を紫染に用いた。実に人造染料使用の嚆矢であった。」と日本染色新報社編『京都染業家名鑑』大正15年刊に山本道三なる人物の「京都の染色業」の稿がある。また、京都府内務部『京都府著名物産調』に「元治(1864)の頃、唐紫(アニリン染料)の輸入以来、其光沢の美なると、其価の廉価なるとに由り人皆争ふて之を用い、爾来アニリン色素を使用す益盛」とある。利便さに富む技術革新には、国境のないことを物語っている一節である。
色素・色料とは物を着色する成分を指し、染料は糸・布の繊維の中に色素を浸透させて染めるものであり、表面に色料を塗るものを顔料と称して分けている。
天然と合成の色素使用をめぐって激しく競合するのは明治初頭からであったが、染料においてはあっけなく合成染料に軍配が挙がってしまった。新奇な利便さと安い価格で天然染料は圧倒された。しかし、恒久な美、芸術的な美を探求するデザインの分野においては、天然染料の優位を今日では実証されており、天然・合成両染料の共生が現代では強く望まれるようになった。
染色界で「染料」となる用語の使用は、合成染料の普及と軌を一にするが、それまでは染草・染艸・染具・染種は植物染料、絵具・顔具は顔料で人造染料は西洋染粉・染粉と称し、その染色を舎密染・新染・粉染と言ったりした。これからのものは萬絵具所・唐和絵具所・諸絵具染草所などで扱っていたが、明治中期には専門の染料商が登場、組合も設立している。
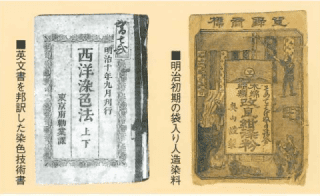
西陣織・京友禅の伝統染織が集積する京都では、明治初頭から官民が技術の近代化に取り組み全国の範となった。明治3年、京都府は中京区に舎密局を設け独人ドクトル・ワグネスを招聘、新技術の指導に当らせ、この年にドイツから合成染料を初めて公式に輸入しているようである。東京府勧業課では英米で出版の絹・綿染法を訳した『西洋染法・上下』を明治10年に刊行して業界を啓蒙。京都の舎密局は和装染織の近代化に大きな役目を果たした。
明治9年には手描友禅師の広瀬治助翁が合成染料による色糊を考案、これが型染め友禅(写し友禅染めとも称す)という画期的な模様染めを創始して、廉価で量産される型友禅染めは大衆に歓迎された。西陣織においても合成染料時代を迎え、全国津々浦々の染織界も新潮流を受け入れて行った。