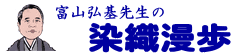前号でご紹介したように、桃山時代に大輪の花を咲かせた「辻が花小袖」の本来の姿は“麻地に大絞りを配した模様帷子(もようかたびら)”、町衆や桂女(かつらめ)などが着る庶民的な衣であった。慶長8年(西暦1603年)、日本イエズス会編纂「日葡辞書(にっぽじしょ)」には“ツジガハナ”とは「赤やその他の色の木の葉模様や文様で彩色してある帷子」の明記がある。
「辻が花」を現代語では小袖や胴服(どうふく)など絹物の絞・墨の描絵・摺箔・刺繍を併用した絢爛の小袖を指して言われるが、この小袖が実際に着られていた当時は“ツジガハナ”とは呼ばれていなかった。単に絞染めに黒描絵・摺箔・刺繍で加飾した高級で、特権階層の人たちが着る小袖であり胴服(胴衣から羽織が派生する)だった。辻が花とは日葡辞書にも記されているように、絞染め模様を施した麻地の帷子を指す用語であると、河上繁樹氏は『蜷川新右衛門知親元日記(にながわしんえもんちかもとにっき)』(寛正6年)、『宗五大艸紙(そうごうおおぞうし)』(大永8年)、『信長公記(しんちょうこうき』(天正9年)、『西洞院時慶日記(にしのとういんよきよしにっき)』(文禄2年)、『太閤記』(文禄2年)などの文献を検証した上で、桃山時代を中心とする時期においては、その意味が今日とは異なっていたと指摘された。
さらに河上氏は、古語(当時の用語)では帷子に絞染めなどで模様を施したものを指すが、現代語では絹の小袖や胴服などに特有な絞染めのあるものを指すようになったと指摘しておられる。
つまり誰かが、その意味を取り違えて公言したことによって、その解釈が独り歩きしてしまった。取り違えた人とは、野村正治郎氏であるというのが有力な見方である。明治12年に京都の美術商の五男として出生。京都市東山区新門前小堀西入ルで古美術商を営んでいたが、昭和18年に他界した。高潔な人柄で氏の営む店には文人墨客、数奇者、外国人の訪問が絶えず、野村氏の審美眼によって選りすぐられた品々に魅せられ、その優れた見識は斯界で高く評価されていた。
大正末期に来日した米国の富豪ロックフェラー氏との「束熨斗模様振袖紅紋縮緬地友禅染・縫箔」(現在、重要文化財指定)をめぐる心温まるエピソードは、紙幅の都合で触れられないが、昭和10年初春に日本で最初になる「キモノ博物館設立の急務」を提案したのは卓見といえる。
「辻が花」を現代語では小袖や胴服(どうふく)など絹物の絞・墨の描絵・摺箔・刺繍を併用した絢爛の小袖を指して言われるが、この小袖が実際に着られていた当時は“ツジガハナ”とは呼ばれていなかった。単に絞染めに黒描絵・摺箔・刺繍で加飾した高級で、特権階層の人たちが着る小袖であり胴服(胴衣から羽織が派生する)だった。辻が花とは日葡辞書にも記されているように、絞染め模様を施した麻地の帷子を指す用語であると、河上繁樹氏は『蜷川新右衛門知親元日記(にながわしんえもんちかもとにっき)』(寛正6年)、『宗五大艸紙(そうごうおおぞうし)』(大永8年)、『信長公記(しんちょうこうき』(天正9年)、『西洞院時慶日記(にしのとういんよきよしにっき)』(文禄2年)、『太閤記』(文禄2年)などの文献を検証した上で、桃山時代を中心とする時期においては、その意味が今日とは異なっていたと指摘された。
さらに河上氏は、古語(当時の用語)では帷子に絞染めなどで模様を施したものを指すが、現代語では絹の小袖や胴服などに特有な絞染めのあるものを指すようになったと指摘しておられる。
つまり誰かが、その意味を取り違えて公言したことによって、その解釈が独り歩きしてしまった。取り違えた人とは、野村正治郎氏であるというのが有力な見方である。明治12年に京都の美術商の五男として出生。京都市東山区新門前小堀西入ルで古美術商を営んでいたが、昭和18年に他界した。高潔な人柄で氏の営む店には文人墨客、数奇者、外国人の訪問が絶えず、野村氏の審美眼によって選りすぐられた品々に魅せられ、その優れた見識は斯界で高く評価されていた。
大正末期に来日した米国の富豪ロックフェラー氏との「束熨斗模様振袖紅紋縮緬地友禅染・縫箔」(現在、重要文化財指定)をめぐる心温まるエピソードは、紙幅の都合で触れられないが、昭和10年初春に日本で最初になる「キモノ博物館設立の急務」を提案したのは卓見といえる。
また、氏の入手した桃山・江戸期の小袖類を屏風百面に貼り付けた「誰が袖衣装屏風」百図は重要な文化財となっている。
話を戻して、野村氏は店で扱う小袖の類で明らかに一つの美の流れを感じさせるものに着目していた。見事な絞染めの彩りと加飾が絶妙に調和した小袖。これを氏は「辻が花」と称して顧客に手渡した。
話を戻して、野村氏は店で扱う小袖の類で明らかに一つの美の流れを感じさせるものに着目していた。見事な絞染めの彩りと加飾が絶妙に調和した小袖。これを氏は「辻が花」と称して顧客に手渡した。
野村正治郎著『友禅研究』大正9年・芸艸堂刊の一節に「絞染の一種なる辻が花染の名は室町時代に始まる大絞りのことで、最初其染生地は奈良晒など麻布に限られたやうであったが、後には絹にも用ひられた。今日俗に云ふ桃山絞は絹を染生地とした辻が花染の進歩したものである。」ととらえている。
これは野村氏流の思考による解釈であるが、この道の見識者で知られる氏の言葉には重みがあった。名称の取り違えは、この著書執筆以前のことと思われるが、他の人たちはそれを信じて疑わなかった。
それを示すのは、大正13年11月に染織コレクターで絵師の楠瀬日年氏が上梓した『古ぎれ集』(私家本)の第一番に掲載の小袖は(前号で写真掲載)現代語解釈の辻が花染であるのに、一言も辻が花とは記さずに「桃山時代絞り染。桃山時代のものにして、紫、黄、緑はすべて絞りなり。花模様は、かき繒にして肩裾模様となり居れり。地は半練りの所謂慶長絹なり。」この時点では辻が花とは云っていない。
それを示すのは、大正13年11月に染織コレクターで絵師の楠瀬日年氏が上梓した『古ぎれ集』(私家本)の第一番に掲載の小袖は(前号で写真掲載)現代語解釈の辻が花染であるのに、一言も辻が花とは記さずに「桃山時代絞り染。桃山時代のものにして、紫、黄、緑はすべて絞りなり。花模様は、かき繒にして肩裾模様となり居れり。地は半練りの所謂慶長絹なり。」この時点では辻が花とは云っていない。
野村氏流の拡大解釈に端を発して今日の“辻が花染め”解釈に至ったというのが、この稿の結びであるが、では本来の帷子の辻が花染めの遺品はどこにあるのか。
絹の小袖な一度も洗われることはないが、庶民的な帷子は洗って使い込まれ、その都度に色褪せ、やがては朽ちる。それ故に数百年後の今日に形をとどめることはなかったと、私は思っている。