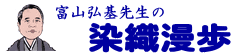世界のファッション界で名高い彩りは「ジャパン・ブルー」。
“日本的な冴えた青色”、言い換えると日本の藍染めに見る日本人好みの美しい青色を示している。
明治8年に時の政府の招きで、来日した英国の化学者“アトキンソン”が目を見張ったのは、暮らしの中に深く根付いている藍色の衣装や布類だった。それに、いたく感銘した彼がその彩りを「ジャパン・ブルー」なる言葉で表現したのは130年前のこと。
日本では藍色・紺・納戸色・縹(はなだ・花田)など様々な色名があり、古く平安朝の『延喜式』(康保4年施行・西暦967)の「雑染用度(くさぐさのようど)」には深縹(ふかきはなだ)など、藍がかかわる15種の色名をあげている。これらの染の藍草は古代に中国から渡来した蓼藍(たであい)であるが、近世から現代にいたる藍染め処の紺屋では、藍染めの淡い“甕のぞき”から染め重ねて濃くなった“搗返し”まで12段階の色目に染め分ける技を持っている。
藍色を染める藍草は含藍植物(インジコ/藍色素を含む植物)と呼ばれる中で日本においては阿波藍で知られる蓼藍(タデ科)の蒅藍(すくもあい)の醗酵建てで本土全域の染織品を染めているが、南島の沖縄県下で、異種の藍草を使って染めている。
南方系のキツネノマゴ科の琉球藍とインド原産のマメ科の印度藍を泥藍にして、これを醗酵建てで染織品を染めている。蓼藍は宮古上布の苧麻糸を染める時のみに琉球藍に少量の蓼藍を加えた併用の藍液をつくっているが、その他は琉球藍と印度藍のいずれかで染めている。この2種の藍草は本土の蓼藍のように中国から持ち込まれたというような人為的なケースでなく、植物の分布上から自生していたものと見られているが、列島の藍染めは3種の藍草から青き彩りの藍色を染めていることになる。
他に、エゾ大青(えぞたいせい/アブラナ科)という藍草が北海道に自生するが、アイヌの人たちが染めに使ったということはない。また忌衣(おみころも)の摺り染めに使った山藍(タカトウダイ科)には藍色素は含まれず、その葉や根から採った樹液で青色の色を染めていたようである。
“日本的な冴えた青色”、言い換えると日本の藍染めに見る日本人好みの美しい青色を示している。
明治8年に時の政府の招きで、来日した英国の化学者“アトキンソン”が目を見張ったのは、暮らしの中に深く根付いている藍色の衣装や布類だった。それに、いたく感銘した彼がその彩りを「ジャパン・ブルー」なる言葉で表現したのは130年前のこと。
日本では藍色・紺・納戸色・縹(はなだ・花田)など様々な色名があり、古く平安朝の『延喜式』(康保4年施行・西暦967)の「雑染用度(くさぐさのようど)」には深縹(ふかきはなだ)など、藍がかかわる15種の色名をあげている。これらの染の藍草は古代に中国から渡来した蓼藍(たであい)であるが、近世から現代にいたる藍染め処の紺屋では、藍染めの淡い“甕のぞき”から染め重ねて濃くなった“搗返し”まで12段階の色目に染め分ける技を持っている。
藍色を染める藍草は含藍植物(インジコ/藍色素を含む植物)と呼ばれる中で日本においては阿波藍で知られる蓼藍(タデ科)の蒅藍(すくもあい)の醗酵建てで本土全域の染織品を染めているが、南島の沖縄県下で、異種の藍草を使って染めている。
南方系のキツネノマゴ科の琉球藍とインド原産のマメ科の印度藍を泥藍にして、これを醗酵建てで染織品を染めている。蓼藍は宮古上布の苧麻糸を染める時のみに琉球藍に少量の蓼藍を加えた併用の藍液をつくっているが、その他は琉球藍と印度藍のいずれかで染めている。この2種の藍草は本土の蓼藍のように中国から持ち込まれたというような人為的なケースでなく、植物の分布上から自生していたものと見られているが、列島の藍染めは3種の藍草から青き彩りの藍色を染めていることになる。
他に、エゾ大青(えぞたいせい/アブラナ科)という藍草が北海道に自生するが、アイヌの人たちが染めに使ったということはない。また忌衣(おみころも)の摺り染めに使った山藍(タカトウダイ科)には藍色素は含まれず、その葉や根から採った樹液で青色の色を染めていたようである。